フランスのように大陸続きで国境を跨げると、
人の往来だけではなく、モノの行き来も簡単です。
バカンスは自家用車でスペインまで~...っていう同僚もいます。
日本は物理的に「海を渡ると外国」ですが、
フランスの場合、「道を隔てて急に外国」になります。
ドイツとフランスの国境近くに住んでいる人は、
当たり前のように独仏二か国語を話したり、
子どもをどっちの国の学校に行かせようか、という選択肢もあるようで。

上の地図のように、フランスは、
・ドイツ
・ベルギー
・スイス
・イタリア
・スペイン
6つの国と国境を持っています。
飛行機や電車で移動する場合はパスポートコントロールがあるものの、
自家用車で移動する場合、基本、コントロールはないと聞きます
(経験したことないのであくまでも伝聞)。
さて、ここから本題。
日本では日本語表記以外の商品パッケージを見ることはほぼ皆無。
おしゃれなスーパーや Costco などでは、外国語パッケージのまま
それを「売り」にして販売しているところはあるものの、
基本、日本語表示のものがほとんどですよね。
フランスでは、基本、二か国語以上の表記がデフォルトです。
これ、10年前に渡仏して初めてスーパーに買い物に行って気づいたこと!
で、消費者もそれに慣れていて、特にデメリットとは考えていません。
自分が読める文字があればそれを読むし、
読めなかったら読めなかったで、パッケージのイラストや商品の陳列コーナーから
わかる範囲で意味を推測します。
フランス語で表記されていなくても、イタリア語やスペイン語は語源が近いので、
結構わかるそう。
ここ最近、うちで買った商品のパッケージも、たとえば…
子どものクッキー(フランス語とポルトガル語)
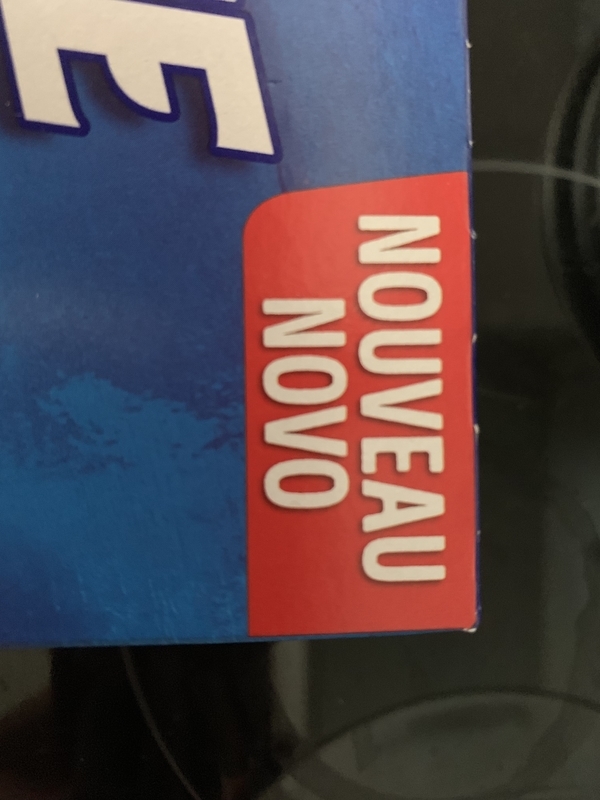
どちらも同じ大きさで表示されているので、
フランス人が見てもポルトガル人が見てもパッと見てわかります。
ポルトガル語とスペイン語は近いので、スペイン人にもメッセージが伝わる。
歯磨き粉はこれ。
(フッ素配合で歯医者さんに薦められたもの)

これは、パッケージ4面のうち、一面が言葉での説明。
左側がフランス語、右側はオランダ語。
フランス語が読めなくても歯のイラストがあるので、
いわゆる効果を説明してる、っていうのはわかる。
左右で同じ情報を書いてたり、上下で分けてたり。
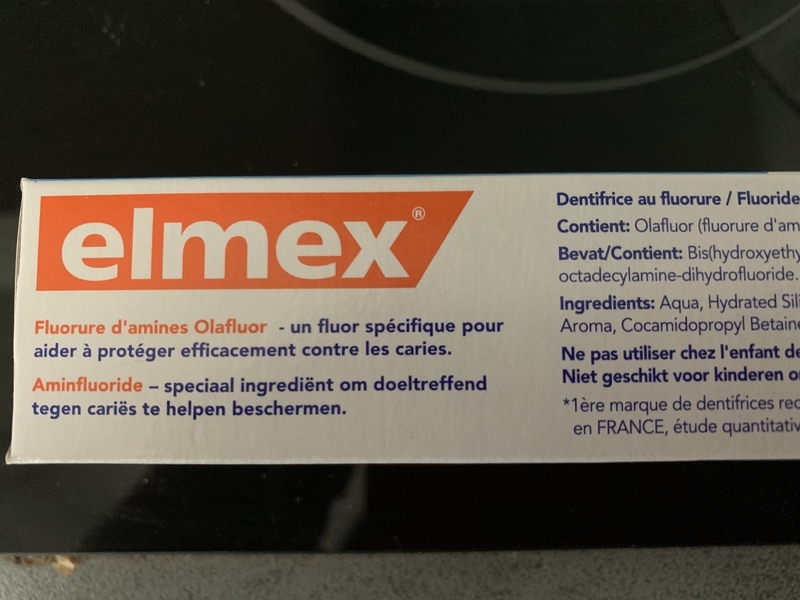
日本でも、ZARAやGAPの製品には、これでもか!というくらい
ベロベロっと長ーい品質表示タグが付いてます。
一方で、衣料品に限らず
食品や衛生用品に多言語表示されているのはフランスならでは、という印象です。
フランスのこのシステム、私はとてもいいと思っていて。
ある国(場所)である商品の売り上げが良いことがわかれば、
そのまま別の国に持って行ってすぐに売ることができる。
品質表示はEUで統一されているので問題なし。
パッケージも多言語表記済みなので、翻訳する手間なく
すぐにお店に並べることができる。
これって、すごく便利で効率的!!
追加でマーケティング費用をかけなくても、
シンプルな欧州大陸共通のデザインにすれば、
フランス、イタリア、ドイツ、スイス... などなど、どこでも使いまわせるわけだし、
パッケージ自体もわざわざ販売管理費をかけて翻訳してシール貼り直して...
という手間がかからない。
なんで日本にはこのシステムがないのか、私なりに考えてみました。
- 海を越えて「日本向け」の商品が押し寄せてくる。...で、日本で消費(購入)されるので、100%「日本仕様」という規格で問題なし。
- 近隣国の嗜好が違いすぎて、そもそも消費(購入)するものが全く異なる。
- 日本人は、日本語、あるいは英語以外の外国語表記があると、怪しんで手を出さない→結果売れない。なので、各メーカーは基本日本語のみ対応することにしている。
- ここを効率化したら、仕事がなくなって困る人がいる(日本はいま労働人口不足と聞きますので、これはあんまりなさそう) 。
日本と違ってフランスでは
なぜこの「多言語パッケージ」が受け入れられているのか、についての推測は…
- 文字が共通(アルファベット)だから近隣国との言葉の壁がそれほど高くない
- 完全フランス語表記じゃないと困る人がそれほどいない。「made in France」を好む人が少ない(競争力がないと思い、割高な印象を与えてる?)。
- 特に何も考えていない。もしくは生まれた時からこれだから気づいてない。
というところかと...。
パッケージの多言語化。
効率を求めて、日本でもどんどん導入されると予想します。
その場合、何語と何語が加わるのでしょうか。
やはり、地理的に近い韓国語、中国語?いえいえ、英語かも?
(そしたら韓国、中国だけじゃなくシンガポールやら豪州まで対応できるし)
色々と想像は尽きません。
では、今日はこれまで。
今日のおとも。
BLACKPINK 'Shut Down'
BLACKPINK の影響力はフランスでもすごくて、
韓国語のBLACKPINKの曲を、韓国語で歌ってた!
アジア発の女の子グループって可愛い系のイメージでしたが、
BLACKPINKは強い女の子!って感じでわたしも好き。
フランスでもそのうち「ガールズグループの曲は韓国語!」っていうのがデフォルトになるかも。
追伸)
そういえば、そういえば、ダイソーは基本、日本語と英語表記!
里帰りの時に買いだめした子どものシールブックやら、
便利な台所用品やらのパッケージも、日本語の横に、小さく、
でもちゃんと英語で書かれてます。
私が知らないだけで、プライベートブランドあたりでこの風潮が始まってそう。
歯磨き粉といえば歯の話!
一生自分の歯で食べる!
子ども関係の記事はこちら~
*1:
話が逸れますが、大阪の超激安スーパーで、明らかに日本人が監修していないであろう日本語表記のパッケージは見たことがあっても、フツーのスーパーではまだまだ一般的ではないです。